
みなさんこんばんは。
今夜のブログは更谷が担当いたします。
Contents
今日は早速、おすすめ動画を紹介します。
『インプラントメインテナンス
インプラントの基礎知識編①〜インプラント治療とは?〜』です。
この動画では、自分の基礎知識の確認はもちろん、インプラントが初めての患者さんへ、説明にも使える内容になっています。
プレミアム動画になりますが、一話は無料公開していますので
是非、ご覧ください!
ラプレッスンの新しいコンテンツとして
インプラントのメインテナンスが追加されました。
そこで皆さんが日頃不安に思っているであろうインプラントについて、
よくある質問にお答えします!

先日行ったインプラントの学会でも、
「 難しい議題ですよね。」と話されていたこの質問。
A. 様々な考え方がありますが、疾患を発見し対処するためにはプロービングを行うことが推奨されています。
ただし、プロービングを行う前の診査が
何より大切だとお伝えしたいです。
まずは視診、発赤や炎症症状が認められないかを目で見て確認します。
前回と比較するためにも口腔内写真などの定期的な資料採取が重要です。
その後、練成充填器などで周囲歯肉を軽く抑えて、排膿などの症状がないかも確認していきます。
異常が認められた場合、デンタルなどのX線写真を撮影しましょう。
骨の状態を把握するためにX線写真(またはCT)は非常に有効な判断材料です。
インプラント埋入後や上部構造が入ったタイミングで撮影しておくと、状態比較できて良いでしょう。
そして、X線写真を確認しながらプロービングを行なっていきます。
この時にとっても大事なことは、
『インプラント周囲のプラークを除去してから』
プロービングを行うことです。
私たちが行うプロービングで、プラークをインプラント周囲に入れ込んでしまうことがないよう注意が必要です。
この際のプロービングは、ドクターが行う医院もありますので、お勤めの医院の考え方に準じてください。
A.最近では使用するプローブは、ステンレス製のものでもプラスチック製のものでも良いとされています。ただし、∗エマージェンスアングルが大きいと、挿入しにくい場合があります。
(∗エマージェンスアングルが大きいとは、インプラント体の径に対して上部構造のカントゥア(補綴物の豊隆)が大きいこと)
しなりのあるプラスチックプローブのほうが
挿入しやすいとされています。
それでも挿入が難しい場合は
上部構造を外してからプロービングを行うこともあります。

インプラント周囲の適正なプロービング圧は15gです。
動画でも、岡村がお話ししてますので見てくださいねー
A. 現在の論文上では、健康な歯肉であれば戻ると言われています。

インプラント周囲のプロービング時には
健康な歯肉であっても出血が認められることがあります。
点状の出血であれば概ね問題ないと判断しますが、線状または流れる出血がある場合は、インプラント周囲粘膜炎もしくはインプラント周囲炎を疑います。
出血の質もチェックしてみましょう。
10月末にはラ・プレシャス運動会。

その1週間後にはラプトレTOKYO。

この後もたくさんのセミナーやイベントを控えている11月です。
そして私ごとですが、またひとつ歳を重ねました。
ラプトレTOKYO真っ只中に迎えたお誕生日。
みんなで仲良く宿泊していた宿で
朝からハッピーバースデーの歌と行進で
メンバーにお祝いしていただきました。

大好きな人と過ごせるお誕生日、幸せ!!!
イベントなどの準備で大多忙のなか、目録まで準備してくれていました。嬉泣🥹
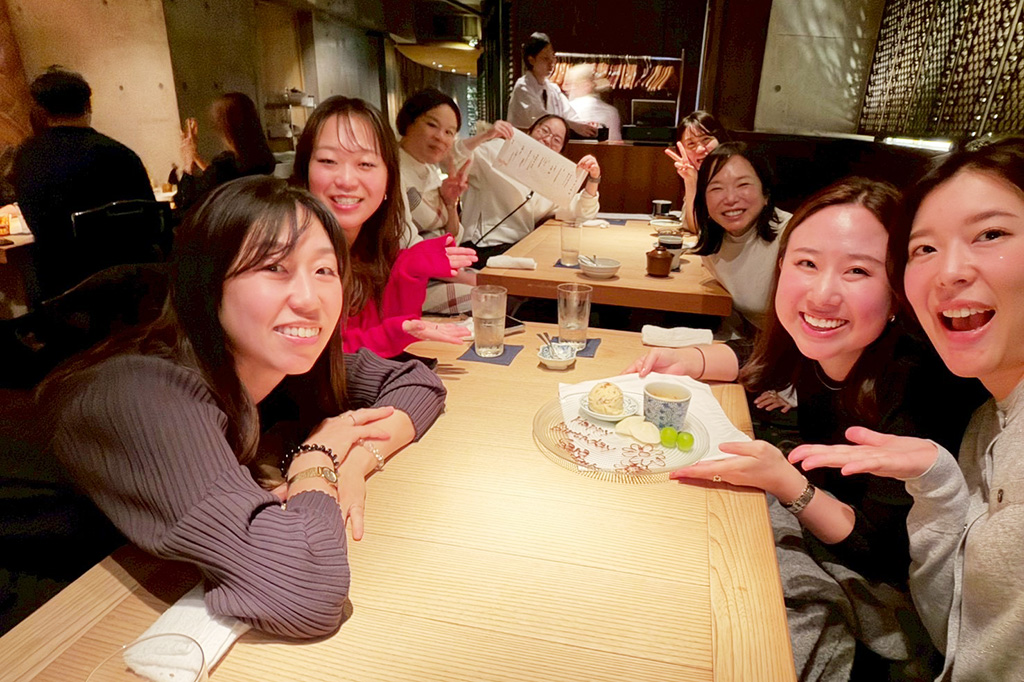
セミナーも大成功に終わり
打ち上げでもお祝いしてもらい
最高の1日になりました!
代表の岡村と出会って16年が経ちました。

新卒で入社した歯科医院にて
『今日はフリーランスの衛生士さんが来るからね。』
と言われ、小心者だった私は
どんな厳しい衛生士さんが来るんだろうと
内心ドキドキしていました。
そんな思いとは裏腹に、
今も変わらぬとびっきりの優しい笑顔で
全身にキラキラを纏って颯爽と現れた岡村。
こんなに優しく愛に溢れた指導者がいるのかと一瞬でその魅力に引き込まれ、
その日のうちにこんな衛生士さんになりたい!
と憧れの存在になったことをよく覚えています。
そしてその想いは今もずーっと変わりません。

私が岡村をきっかけに歯科衛生士の仕事を大好きになったのと同じように、
私も誰かにとって希望を与えられる存在になれるようがんばるぞー!

インプラントのメンテナンスは、オペの前から始まっています。
インプラントを長持ちさせるために患者さんに知ってもらうべきこと、患者さんとの関わり方や各フェーズでのポイントをお伝えしています。
患者さんと二人三脚でインプラントを守っていくために、
私たちがまず知っておくべきことを学んでみましょう!

大臼歯部のデンタル撮影方法です。
口蓋の浅い方や口蓋隆起のある方で、インジケーターが口腔内に入りにくい方への対処方法などもお伝えしています。
正しくスムーズな位置付けで
読影しやすいデンタルを目指しましょう!
歯科衛生士の診療に
役立つ情報を発信!